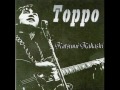杳子・妻隠(つまごみ) (新潮文庫)
収録されている2作ともレベルの高い小説です。とくに『杳子』は作者の特徴を非常によく表しており、登場人物の精神状態の不安定さが、より深く読者をストーリーに引き込みます。読者の感情をぐらぐら揺さぶる力をもった小説だと思います。

野川 (講談社文庫)
読み終えたとき、これはある種の遺書なのではないか、と思った。古井氏の、古井文学の、そして文学それ自体の遺書なのではないか、と。
大袈裟な言い方かもしれない。
しかし、この作品のなかで起こっている事態はただ事ではない。なによりも、言葉の存在論的な無重力化ともいうべき出来事が、従来の古井節を廃棄する形で、ひそかに生起してしまっているということ。この実に特異で奇跡的な〈軽さ〉をおのれの書法において実現してしまった後で、なおも文を書き継ぐことが果たして可能なのか? この作品を「ある種の遺書」と呼んだのは、まさにこの意味においてである。
にもかかわらず、この作品を書き終えた古井氏は、まるでなにごとも起こらなかったかのような涼しい顔で、すぐさま新たな連載(『辻』)に取りかかる。
いやはや、おそるべし、と言うほかない。

どうせなにもみえない―諏訪敦絵画作品集
NHK日曜美術館で、「記憶に辿りつく絵画〜亡き人を描く画家〜」が2/19,2/26にアンコール放送される!
私自身のものも含め、Amazonのレビューなんてすべてスルーして、この本を体験することだ。
それがなにより大切だ。
何を感じるか、作品を手元に置くかは、あなた次第。
是非、手元に置いて欲しいと個人的には願う。
しかし、この表紙の絵を見て何も感じなかったら・・・出会いはなかったということになるだろう・・・。

人生の色気
思い出したのは吉本隆明さんが語り下ろしでしか本を出せなくなってからの『僕なら言うぞ!』『13歳は二度あるか』『よせやぃ。』などの本。それまでの読者から大きくかけ離れた層に、あえてイメージを壊して、けっこう下世話に語りかけている点が似ているかな、と。
古井さんが手取りの月給が10万円に届いていない時代の大学教師を辞めて書いた第一作は240枚の『杳子』ですが、当時の文芸雑誌の原稿料は600円から1000円なので、当分の計算は立った、なんていうあたりから語り始めます。当時、「自己解体」をスローガンに学園紛争に熱中している学生たちを、古井さんは《目に見えない何かに対するツケのようなものを支払っている風に見えました》(p.23)と書いていますが、それが可能だったのは経済成長を当たり前だと考えていたからだ、と。そして《経済は人の社会を外部から根本的に変えてしまい、どう変わったのかも気づきにくい》とも。
そんな話から、《不祝儀の場の年寄りの振舞いに、男の色気は出るもんなんです》《喪服を着て、お焼香をして、挨拶して、お清めをして帰ってくるだけのことが、いまの男は、なかなかサマにならない》(p.44)なんあたりに飛んで、さらに男に色気がないから、いまの女性の化粧は他人を拒絶するような印象を受ける、というところまでいきます。
《人間には、破壊の欲望があるもんなんです。すべてが壊された時、人は解放される。人はそれぞれ、過去にろくなことを抱え込んでいないでしょう》(p.61)なんてあたりもいいな。

蜩の声
現代の日本文学において秀異な古井由吉氏の作品を生み出しているのは、ひとえに老翁の明視と老健でしょうか。
古井氏の作品を読んでいると、官能が澄んでくるのが分かり、これまで己の官能が鈍磨していたことを思い知らされます。五官が捉えていた表層に覆われ隠れていたものに思いを致すようになり、更には思考も澄んできます。
古井氏の作品は過去に内向との誹りを受け、現在でも首を傾げる向きがあるかもしれませんが、その作品は決して内を向いたきりのものではありません。内への強靭な志向は否定できませんが、それを非難することはできないでしょう。内向が極まれば外が開かれはしないでしょうか。
自身の官能による受容とそれを巡る思考の独白とも随筆ともつかぬ叙述。時間的にも空間的にも限られたささやかな物語。その間の一読唐突とも読める往来は、小説の埒外へと逸脱しているように思う向きもあるでしょうが、物語の表層を剥いだ後の、感情や思考さえもが表層でしかない底流で通じ響き合っています。物語を幾何学的に捉えることを止めさえすれば、大きく開かれた官能と自由闊達且つ厳密な思考によって織り成された物語と言えるでしょう。その場では生と死、男と女、過去と現在、あらゆる境域で互いが混じり合い、汽水湖のような鎮まりのなかで睦みが交わされています。
そして本書中最も注目すべきは、末尾の「子供の行方」でしょうか。戦時の悲愴の記憶は、官能にその跡を遺して筆者を苦しめます。思考による記憶は対象化によって恐怖の度を抑えられていても、官能にこびりついた記憶は内に闖入して恐怖の度が抑えられることがありません。老いるに従い、官能の記憶は強度を減じますが、記憶の静まりから恐怖は変わらず膨らんできます。筆者は燥いで忘却を決め込むことなく、常に絶えず恐怖の記憶を語っていくことを自らに課すのです。老いてなお、と言うよりも老いてこその作家の姿勢には心を打たれます。