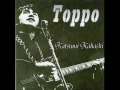お早く御乗車ねがいます (2011-09-22T00:00:00.000)
昭和30年前後の鉄道話。
「いい年した大人が鉄道好きとは」と少々照れながら
「旅」などに書いた鉄道記。
50代以上の鉄道ファンが就寝前に読むには最適。

米内光政 (新潮文庫)
司馬遼太郎氏のような主人公を一から追ったものとは違い、最初から他の人からの伝聞や
資料を元にした推察などで進められ、歴史に無知な者としては、最初誰が誰やら混乱をきたした。
ただそれでも読み進めるにしたがって、だんだん米内さんに引き付けられている自分に気付く。
そして、彼に接した人物たちに、まだ無名であったにもかかわらず「海軍は米内光政ではないか」と
言わせるだけの彼の「何か違うな」と思わせるものは、彼らに語ってもらうのが一番わかりやすく、
説得力のあるものになったのではないかと思う。
また、阿川氏自身が米内があの時勢に異常なまでに冷静であったように、
客観的に米内を見つめた結果なのかもしれない。
写真を調べると、整った顔立ちながら長身で、この人がじっと黙って座っていたらかなり気になるなと思った。

雲の墓標 (新潮文庫)
爆撃機のパイロットとして、戦争とは別に、我々が旅客機で見ているような雲とは別に、様々な雲を見ただろう。
私は飛行機に乗ると、可能な限り、窓側に行って、雲の動きを見ている。
積乱雲もあれば、霞のような雲もある。夕日や朝日で刻々と色を変える雲を見ているのは、自然の営みの象徴のように思える。
これから爆弾を投下しようとか、味方の援護をしようとした日本人パイロットは、灼熱の赤道付近で様々な雲を見ていたのであろう。
そういう中で、これから「殺人」をするなどということは考えなかったのではなかろうか。むしろ、「あの雲が最後に見る雲なのかもしれない」という不安感の中でコックピットにいたのではなかろうか?
そういう航空兵の心情を余すところなく描いた名作であろう。

きかんしゃやえもん (岩波の子どもの本)
生まれてから、今まで読んできた日本の絵本の中で、"これ!!"というものを一冊挙げなさい、と言われたら、私は迷わず"きかんしゃやえもん"を挙げさせていただきます(海外の絵本と言われたら、多すぎて迷ってしまうのですが…)。
この本を読まずに大きくなってしまう日本の子ども達がいるなんて、少し可哀相な気がします(大きなお世話?)。
ぜひ読んで欲しい絵本です。
この本を読まずに大きくなってしまった日本の皆さん、今からでも遅くはありません。
大人になって読み返して、私は初めて"やえもん"の本当の哀しみを感じることが出来ました。

山本五十六 (上巻) (新潮文庫)
山本五十六が、軍神でも英雄でも郷土の誇りでもなく、一人の人間として描かれている。
苦渋に満ちた仕事ぶりと、その反面のばくち好きや芸妓遊び。
山本五十六という人物をあますところなく書き表していると思う。